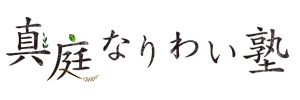8月3日(土)~4日(日)に、第4期真庭なりわい塾の第3回基礎講座を実施しました。今回の講座では、環境、生態系、生活資源、ビジネス、そして精神文化に至るまで、人の暮らしや生業と深くかかわる森林について理解し、人と森のこれからの関わり方を考えることを目的に講座を実施しました。
〇講義「日本の森と人の暮らし」 塾長 渋澤寿一(NPO法人共存の森ネットワーク理事長)
人間は、ここ50年ほどの間、石油などをはじめとする地下資源を使うようになり、大量生産、大量消費、大量廃棄の社会をつくってきました。けれども、そもそも生物である人間は、自然生態系の中で生きています。太陽エネルギーによって成長できるのは植物だけ(植物は光合成によって、太陽の光と水と空気中の二酸化炭素から炭水化物を合成できる)。その植物を食べて、動物も人間も生きているのです。植物は、人間が生きるために必要不可欠なものなのです。
氷河期の日本列島は、暖流が流れ込む日本海という、いわば湯たんぽを抱えていました。なので、日本列島は、生物多様性が豊かな地域になりました。そして日本の森林は世界でも珍しく、ほぼそのすべてに人の手が入った森林です。人が木を伐り、森に光を入れることによって、生物多様性が維持されてきたのです。森の管理とは、人間による光のコントロールです。里山はそのまま放置すれば、クライマックスに到達してしまいますが、人が手を入れて循環的に利用することにより、落葉広葉樹を中心とした豊かな植生が保たれてきたのです。
1660年代半ば、イギリスも日本も森林面積が30パーセント台に減少していました。紡績業が発達したイギリスでは、牧草地を確保するために森林を伐採しました。一方、日本は徳川政権の誕生により、平和な都が栄え、木材の需要が増えました。当時、どちらの国も、森を保全する方策が検討されました。けれども、イギリスは、さらに森林を伐採して産業を振興し、軍艦をつくり、植民地を広げていきました。一方、日本は、鎖国をしました。国内の森林を保全し、限られた資源の中で生きていくことを選んだのです。
明治から昭和にかけての日本は、戦争をするために木を大量に伐採し、森林を荒廃させました。戦後、植林をしましたが(拡大造林)、木材の自由化により、外材が大量に輸入されるようになり、木材自給率は再び30パーセント台になってしまったのです。
森は、私たちの暮らしや価値観そのものを反映しています。自給し、自足する本来の日本人の暮らしが、日本の森の豊かさを守ってきたのです。
秋田県秋田市の鵜養(うやしない)という集落に通ったことがあります。江戸時代に、飢饉でも餓死者が出なかった村です。この村には、共有林が33箇所あり、33年を1サイクルとしながら、順繰りに伐採しています。伐採した翌年、その場所はワラビの宝庫になります。広葉樹は切り株から萌芽しますので、30年経過すれば、また、元の里山に戻ります。持続可能に利用してきた里山は、衣食住に関わる、すべてのものを与えてくれました。
山形県小国町金目では、「栗林1町(1ヘクタール)、家1軒」という言い伝えが残っています。栗林が1ヘクタールあれば、たとえ米が収穫できなくても、家族が餓死することなく、生きていけるのです。
山形県飯豊町中津川の広河原集落では、一軒だけ残った民家に、お爺さんとお婆さんが暮らしています。屋根葺くための茅を刈り、菅やガマを刈って笠やゴザをつくり、燃料の薪や炭はもちろん、山菜や木の実。昔は牛馬にやる草も、ありとあらゆるものを里山から得ていました。そして、今も山に杉を植林し、夏の暑い盛りに、下草を刈っています。そうした生き方は、山に対しての当たり前の作法なのです。そして、この地域には、草木に感謝する「草木塔」の石碑があり、お爺さんは「今日も生かされて、ありがとう」と感謝の祈りをささげます。
自然を利用し、人間が持続可能に生きていくためには、「自然が復元する時間」「自然の量」「自然の質」、そして「人間の労働」や「知恵と技術」が必要で、何より、このお爺さんのような「心の置き方」が問われるのです。
〇映画「奥会津の木地師」の上映
「日本の森と人の暮らし」の講義が一段落したところで、民族文化映像研究所が製作した「奥会津の木地師」という映画を鑑賞しました。かつて山を移動しながら暮らしてきた「木地師」(お椀などの木地をつくる職人)の記録映像です。はじめに、木地小屋(木地師が山の中で作業をしながら暮らす小屋)を建てるシーンから映画は始まります。その場で伐り倒した木材で骨組みをつくり、笹で屋根を葺いていく。そして、山の水を小屋の中に引き、作業場をしつらえる。神様の祠も自分でつくって、祈りをささげます。伐採したブナの木からお椀の荒型を掘り出し、中を刳り、手引きのロクロで整形していく木地師ならではの技術はもちろんですが、生きることのすべてを自分たちの手でつくりあげていく、その姿に圧倒されます。
上映後には、山菜やキノコ栽培など、誰でも気軽に楽しみながら少しのお金に換えることができる、そんな里山資源の活用事例を、いくつか聞かせていただきました。
〇広葉樹の森を歩く/一社アシタカ・木材活用の見学
講義の後は、津黒いきものふれあいの里に出かけました。副館長の多久間稔さんと中和地区の山仕事の達人、池田清一さんを講師に、小林加奈さん(真庭なりわい塾事務局長)の案内で里山を歩き、炭焼き窯を見学し、里山の植生の変遷、樹木のさまざまな活用、炭焼きや山仕事の道具などについて教えていただきました。ここでは古い時代に「たたら製鉄」が行われていたこと、木地師が活躍した時代があったことなど、中和の山の歴史についても伺いました。
その後、一般社団法人アシタカの薪土場に移動しました。赤木直人さんから、中和薪生産組合と共に津黒高原荘の薪ボイラーに薪を燃料として供給する仕組みをつくった経緯などとあわせて、現在、キャンプ場や個人向けにも薪を販売し、しんたけ栽培のほだ木としても活用していることなどを聞きました。そして、燻製大根(いぶりこうこ)やクロモジ茶、アロマオイル、アクセサリーなど、里山には、さまざまな活用の可能性があることを改めて教えていただきました。
里山とその活用について学んだ翌日は、林業について学びました。
〇林業・間伐作業の見学
真庭なりわい塾の一期生である大岩功さんが、さまざまな体験プログラムを企画・実践している「はにわの森」の一角で、中和地区に移住した木こりの和田厚志さんに間伐作業を見せていただきました。立ち木をチェーンソーで伐採し、枝を払い、玉切りしていく和田さんの動きには、まったく無駄がありません。作業は終始、安全にも配慮しながら進めていき、一本の木が素材丸太へと生まれ変わりました。その後、和田さんには、山での作法や木こりの道具などについてお話を伺いました。
〇講義「林業とバイオマス」 塾長 澁澤寿一
日本のスギは、世界一安いといわれています。40~50年生のスギの木が、山では一本500~600円で取引されているのが現状です。皆さんが木造住宅を買うとします。住宅価格のうち、木材価格は2~3割。ほとんどは、キッチンやお風呂などの水周り、あるいは空調や太陽光といった設備費なのです。消費者は白い色の家具を好むので、国産材はなかなか使われません。昔の家づくりは、山で木を選んで、伐採し、それをじっくり乾燥させるところから始まりました。実際に家を建てるまでには何年もかかりましたが、今は住宅納期も短くなっています。家は、100年使うのが、昔は当たり前でしたが、現在の住宅の耐用年数は24年ぐらい。「子どもが大きくなったら、親はマンションなどに住み替える」といったように、住宅も消費財になってしまったのです。林業界の課題には、人手が足りない、儲からない、後継者がいないなど、さまざまありますが、実は消費者の価値観の変化が一番の問題です。
一方で、日本の人工林は現在、50~70年生の木材蓄積量が最大となっています。伐期を迎えた木はたくさんある。でも、伐らない。そして、その前後の樹齢のものは少なく、コンスタントな山の管理にはなっていないという現状があります。
現在、国の施策は、林業に対しても、大型機械をフル稼働するような生産性、効率性が求められています。でも、山は生き物です。競争力を高めることばかりを考えて、むやみに大量伐採すれば、その弊害が必ず出てきます。林業を持続可能にするためには、林齢の偏りをどう解決するかを考えなければなりません。一方、なりわいとして林業を考える場合には、農業などと兼業で山を活用したり、伐った木を余すところなく使う工夫をしたり、さらに山村振興につなげるなど、さまざまな可能性があるように思います。
真庭市は、木質バイオマスの活用の先進地といわれ、「里山資本主義」という言葉で有名になりました。でも、20年ほど前までは、山には何の価値も見出せない、どこの山村とも変わらない状況でした。当時、製材所やコンクリート会社、酒造会社などの若手経営者が集まって「21世紀の真庭塾」を結成しました。1997年、彼らは「2010年真庭人の一日」という物語を描いています。13年後の、ある一日を描いた物語です。ここにいる皆さん、すべての人に確実にいえることは、13年後には13歳、年をとるということです。ここには子供たちに大人気の温水プールがあり、地元製材所の木質バイオマスエネルギーが使われているといったことが書かれていますが、13年後に検証してみると、ここに書かれていることの8割は実現していたのです。未来は政治家がつくるものでも、コンサルが描くものでもない。自分たち自身で思い描き、つくるものなんだと、私は真庭の皆さんから学びました。
当時、真庭(旧勝山町、久世町、落合町)には、製材所が32軒ありましたが、どの製材所も経営は厳しかったです。なぜならば、木材しか扱っていなかったからです。一方で、ヨーロッパの製材所は、木材の売り上げは全体の7割程度。それ以外に、チップを売ったり、バイオマス発電などをして成り立っていました。
そこで、真庭でも、あらゆることをやってみました。樹皮、木片、プレナー屑、ペレットやチップ、木粉など、ありとあらゆるものを、エネルギーやマテリアルとして利用することを試みました。
ひのきのおが粉と珪藻土を混ぜた猫砂は、大ヒット商品になりました。猫砂の消臭効果によって、都会のマンションでも猫が飼えるようになったのです。
これで、ある程度、仕組みができてきたと思いましたが、製材所から出る木質バイオマスだけでは、安定供給ができないことがわかってきました。建材を生産するラインが止まってしまうと、チップや木粉などの副産物が生産できないのです。そこで、山から直接、風倒木や林地残材など、木材市場では売り物にならないものを集積基地に集める仕組みをつくりました。
集積基地では、どんな木も、トン3千円で買うことにしました。高い、安いといった議論もありました。でも自分たちでその価格を決めて、いままでは価値がないと捨てていたものまで流通するようになったのです。
その結果、1万キロワットの木質バイオマス発電所が完成し、地域内エネルギーの自給率は32パーセントになりました。重油に換算すると、年間約30億円を地産地消するようになったということになります。このお金は、以前は、中近東などの産油国に払っていたお金です。それが地域内循環し、雇用を生み出し、森には価値がないと考えていた山の所有者にも、お金が入るようになったのです。
木材は、重くて、汚くて、かさばります。それゆえに、多くの人がかかわらないと流通しません。木材の価格を自分たちで決めるということは、森の価値を自分たちが決めるということです。全員の思いがまとまらないと、木材は流通できません。
昨日、薪土場を見学させてもらった赤木直人さんは、中和地区の中で、薪が流通する仕組みができたことを、こう評価しています。
「お金の地域内循環が大きな成果ではなく、これをきかっけに、たくさんの人がかかわり、そこに話題が生まれ、協調する仕組みができたこと、これが一番の成果だと思います。……次の世代は、今のままの社会では、豊かに暮らせていけるとは思えません。私は、次の世代に向けて、豊かな暮し方をつくっていきます」
便利で豊かになったといわれる日本は、本当に幸せになったのか。これからの社会をつくる上で、どんな価値観が必要なのか。どうしたら、私たちは自足(満足)できるのか。一番大切なのは心、価値観を変えることです。たとえば、暮らしの安心や育てる喜び、できたものを人に分ける喜び。人と人とが関わり、つながる楽しさ。そういったものが価値になれば、林業も農業も変わるように思います。そして人々の心が変われば、そこには、また新たなマーケットが生まれるのです。
「里山資本主義」は、森が人と人との関係をつなぐ、価値観が変わる、そういうことだと私は思います。
さて、来月は、《地域のお年寄りに話を聞く》と題し、聞き書きを行います。
お話を聞き、文章にまとめることで、その人の人生に寄り添い、農山村で生きてきた人々の歴史や想いを学んでいきます。あわせて、民族文化映像研究所が製作した「越後奥三面-山に生かされた日々」という映画も鑑賞する予定です。
≪講義資料≫
日本の森と人の暮らし① 日本の森と人の暮らし② 日本の森と人の暮らし③