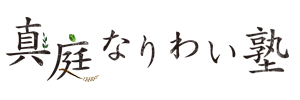2016年12月10、11日(土・日)に真庭なりわい塾の第8回講座を実施しました。
今回の講座は「経済と地域~自分でみつける『豊かさ』と『幸せ』の基準~」と題し、これまでの講座の総まとめとして、講義やワークショップなどを行いました。
初日は、真庭なりわい塾副塾長の駒宮博男氏(NPO法人地域再生機構理事長)の講義からはじまりました。
(※講義資料はこの報告の最後に添付します。)
■講義「地域と経済~これからの幸福論~」
<専門家ばかりの社会の危うさ>
哲学者オルテガが書いた『大衆の反逆』(1929年)という本があります。この本でオルテガが言う「大衆」は、私たち日本人が考える「大衆」とはまったく違います。オルテガは、「大衆」の典型は「専門家」だと言っています。具体的には、技術者や科学者のことです。1900年代の初頭には、そうした「専門家」が次々と出てきました。オルテガは、一分野だけに秀でている「専門家」は「大衆」でしかなく、必要なのは「社会を総合的に捉えるジェネラリストだ」と主張しています。これは今の日本にも通じます。一方、佐伯啓思(京都大学名誉教授)という保守派の経済学者は、『さらば、資本主義』(2015年)という著書で、「専門家が重宝される社会は、所詮、ニヒリズムでしかない」ということを書いています。
<いまだに残存する「成長幻想」>
現代は、資源問題や環境問題、食糧問題などが起きているにも関わらず、いまだに「成長幻想」をもつ人が多くいます。
欲が増殖するのは子どもの世界で、欲を抑制して初めて大人の世界だといえるでしょう。ところが今は、欲をいたずらに増殖しないと回らない経済になっています。そうした経済を作ったことに大きな問題があるのです。一方で、最近の若い人たちの中には、「ミニマリスト」といって、必要なもの以外持たないという新たな価値も生まれています。
成長戦略の結果、物質的には豊かな社会になりました。けれども、精神的には不安定な社会になっています。元ウルグアイ大統領のムヒカ氏は、「貧乏とは物を持っていないことではなく、物を欲しがること」(2012年)だと言っています。
都市に人口が集中して地域が崩壊し、所得や地域格差が拡大したことも、この「成長幻想」が原因だと考えられます。
<ピケティが解明した格差拡大の正体>
フランスの経済学者ピケティは、資本主義社会について「金持ちがより金持ちになる社会である」と言っています。また、ノーベル経済学賞を受賞したアメリカの経済学者スティグリッツも「1%の1%による1%のための政治経済である」と言っています。
ピケティは、資本収益率と経済成長率の関係についても分析しています。グラフを見ると、人間の歴史の中では、資本収益率が経済成長率よりも高い時代が長かったことがわかります。経済成長率が資本収益率を上回ったのは、戦後30年という特異的な時代だけです。ほとんどの時代は、ピケティが言うように、金持ちがより金持ちになる時代であったと言えます。ピケティは、「金持ちの財産にはもっと課税せよ」とも言っていますが、現実にはなかなかうまくいきません。
<世界経済の歴史を概観する>
もう少しタイムスパンを長くして歴史を見てみましょう。『西洋世界と日本』というジョージ・サムソンの名著があります。彼はその本の中で、「大航海時代はイスラムが牛耳る地中海からの脱却であった」と書いています。西欧列強の帝国主義時代には、面白い話も残っています。インドのマハラジャに出向いた際、そこでは純金の痰壷を使っていて、ヨーロッパから持って行った金製のお土産物は出せなかったという話です。
1850年までヨーロッパは圧倒的な輸入超過でした。当時の中国の輸入品は象や美人の女性など非必需品ばかり。挙句の果てに英国の銀は中国へ流出し、これがアヘン戦争のきっかけになりました。このように19世紀中葉まで、ヨーロッパ諸国に対してはアジアが優位だったと言えます。一方、ヨーロッパはイスラムの圧倒的な支配下にありました。『社会科学を越えて』(平山朝治著)には、当時のヨーロッパの文化レベルは、イスラム、東方キリスト教会、西方キリスト教会の順であったと書かれています。その後の19~20世紀は、西ヨーロッパが歴史的鬱憤をはらした200年であったのかもしれません。ですが、西ヨーロッパが築いた近代そのものが、今、崩壊しようとしています。
<「お金」をどう考えるか>
そもそもお金とは何なのでしょうか。日本では、エントロピー学会が、物質は熱力学第2法則に則って時間とともに劣化するが、お金だけが時間とともに肥大する矛盾を指摘しています。 肥大するものは何かというと、「利息」です。「利息」は、「あなたはいくらの利率で借金可能か」という「信用度」です。高い利率で貸すということは、返ってこない可能性がある、つまり「信用度」が低いからです。
『貨幣論』(岩井克人著)には、「つまるところ、貨幣には何ら価値はない」と書かれています。また、『貨幣の思想史―お金について考えた人々』(内山節著)には、次のように書かれています。
「貨幣は、つねに外部のものとして成立し、それが内部に介入してくるかたちで、有用性の貨幣化という虚構をつくりあげていく。交換の必然的結果として貨幣が生まれたのではなく、貨幣が生まれ、介入してきたことによって、交換が貨幣化されたのである」
つまり、モノを交換するために、お金は便利だからといって貨幣が生まれたわけではなく、単に貨幣が生まれたことで貨幣は貨幣として成立したのだ、ということです。
<忘れ去られた労働観とシャドーワーク>
次に労働について考えてみましょう。アダム・スミスは、労働が本源的な価値だという労働価値説を主張していました。一方、マルクスは「労働は第一に、人間と自然との間の一過程である」という労働過程論を主張しました。どちらも労働だけが価値を生み、それに見合う対価が発生するという考えです。今は、「モノ」「サービス」「マネー」と価値が分散している状態だと言えます。そして不労所得願望が強い社会になっています。
経済学者のイヴァン・イリイチは、「シャドーワーク」という考え方を提示しました。労働を三角形の氷山に表すと、太陽が照らされている部分だけが賃金労働であり、日陰の部分には、通勤やサービス残業などの不賃金労働があります。さらに、水面下に隠れている氷山の大部分が「シャドーワーク」です。そこには、家事労働、妊娠・出産、子育て、教育が含まれます。地域での奉仕活動や祭りなどの「務め」もまた「シャドーワーク」です。本来は、こちらが人間活動の中心であり、それを支えるのが賃金労働であるべきではないか、というのがイリイチの考えです。これはとても重要な考え方だと思います。
<日本の生きる道は一つしかないのか>
戦後の日本では、資源を海外から調達して付加価値をつけて海外に売ることが、生き残るための唯一の道だと考えられてきました。また、高度経済成長期には、GDPの増加が幸せの増大であるという強い幻想が生まれました。
現在、比較的に豊かな国だと言われているのは、デンマークとオーストリアです。デンマークでは、風力や豚の糞を利用した再生可能エネルギーが発達しており、100%に近い自給率を誇っています。また、セカンドスクール普及しており、「いじめ」がないと言われています。オーストリアもバイオマス大国で、過疎がないと言われています。みなさんは、この2国の商品を何か一つでも持っているでしょうか。ほとんど持っていませんよね。日本製の商品を持っている人は世界じゅうに大勢います。でも、だから日本人は幸せと感じているかというと、そうではありません。何が幸せを作るのか、もう一度考えなければいけないと思います。
<GDPとは何か>
そもそもGDPとは何なのでしょうか。日本のGDPは1995年頃から、ほとんど変化がありません。明らかに定常型社会に入っています。定常型であることが問題なのではなく、経済格差が拡大していることが問題です。そして、これからさらに人口が減少していくということは、これ以上マーケットは大きくなりません。どうしても定常型にならざるを得ないということです。
日本は世界に先駆けて、定常型の脱成長時代に入りました。脱成長でも幸せ度を確保しながら生きる方法を考えなくてはなりません。ジョン・スチュアート・ミルは、150年前に「経済学原理」という著書の中で定常型社会について触れています。彼が考えた定常型社会の理想は、「マクロ指標は不変だが、内部は文化の花が咲き乱れる社会」でした。最近では、セルジュ・ラトゥーシュが「脱成長論」という本を書きました。そこでは、「経済が目的となる社会」から「社会が目的となる経済」にしなくてはならないと主張されています。彼の結論は「コンヴィヴィアリティ」、つまり「楽しみを分かち合うことが必要だ」ということでした。つまり、経済的価値以外の多様な価値が認められる社会をつくることが重要だということです。
<地域の循環経済>
地方創生が叫ばれる中で、いまだに、地域経済を活性化するためには企業誘致が不可欠だという主張があります。果たしてそうでしょうか。確かに付加価値生産の利益の一部は、固定資産税として自治体に徴収され、賃金として地域の従業員に支払われます。しかし、利益のほとんどは本社に吸い上げられているのが現状であり、事業が傾けば、すぐに地域から出て行ってしまいます。これでは地域に貢献しているとは言えません。
一方で、地域の資源を活用する方法もあります。これは真庭がひとつのモデルです。地域の資源を材料として調達するため、地域の従業員が働き、報酬を得る。さらに、材料に付加価値を付けるために、地域の別の従業員が働き、報酬を得る。そして、利益は地域内で設備投資されていきます。この方法であれば、地域に貢献していると言えるでしょう。
<関係性をいかに再生させるか>
真庭では、地域資源を利用することによって経済を循環させていますが、それは、人と人との関係性を再構築することでもあります。循環型経済は、人と人、人と自然、世代と世代の関係性を再構築する経済だと言えるのです。ブータンでは、この3つの関係性が良好な状態であることが幸福の定義です。ところが、今の日本は、これらの関係性が喪失された状況にあります。人と人の関係性おいては、「孤立社会」、「無縁社会」と言われる現象が起きています。人と自然との関係性においては、生産と消費が分離してしまっています。世代を超えた関係性を作ることも非常に難しくなっています。あまりにも目まぐるしく時代が変化し、自分が生きた時代を咀嚼して消化することができないまま、次の世代に伝えられないという状況です。
塾生の皆さんの中には、生きづらい現実から何とか脱却したいと考えている方が多いでしょう。田舎に行けば、心地よい関係性が残されている。だから田舎への移住を考える人もいると思います。しかし、現実の田舎が、本当に理想な社会であるかといえばそうではないかもしれません。ただ、目指すべき社会のヒントはいくつかあります。小規模多機能自治、適性技術社会、定常型社会などがその例です。私たちは模索と試行を繰り返しながら、気持ち良く生きられる社会を作っていかなければなりません。
■ワークショップ「X年後のわたし」
次に、「X年後のわたし」と題して、ワークショップを行いました。X年後、どこで誰とどんな暮らしをしているのか。どんな仕事をしているのか。地域や社会とどのように関わっているのか。夢や目標は何か。そのX年後のために、今、何を具体的にはじめるか。各自、ワークシートに記入した後、3人1組で共有しながら意見交換を行うワークを2回繰り返して行いました。塾生たちは、お互いアドバイスをし合うことで、自分の夢をより具体的に、現実のものとするためのブラッシュアップを行いました。
この「X年後のわたし」は、2月に塾生全員に修了レポートとして発表してもらいます。
2日目は、澁澤寿一氏(認定NPO法人共存の森ネットワーク理事長)の講義からはじまりました。(※講義資料はこの報告の最後に添付します。)
講義の中では、『逝きし世の面影』(経済学者、渡辺京二氏著)から抜粋して、当時の日本人の暮らしぶりが伝えられました。この本は、幕末から明治初頭に来日した外国人が本国に送ったプライベートの手紙を翻訳してまとめたものです。
■講義「未来のための江戸の暮らし」
<江戸という閉じられた生態系>
環境問題を論じるときに、地球はひとつの「閉じられた生態系」であって、宇宙船『地球号』である、という表現をします。鎖国をしていた江戸時代の日本もまた、ひとつの「閉じられた生態系」であり、250年間続いた持続可能な都市でした。それを今の地球に置き換えると、これからの持続可能な社会モデルが見えてくるのではないかと考えています。
「閉じられた生態系」というのは、ひとつの世界の中で果てしなく物質が循環するシステムです。供給されるのは、太陽エネルギーだけです。太陽エネルギーを固定できるのは、基本的に植物しかありません。私たちは、その植物を食べ、死ぬと土に還ります。閉じられた世界の中ですべてが循環していたのが、江戸時代です。
<江戸の風景―自然エネルギーで生きた時代->
石油も石炭も利用されていなかった150年前の日本は、太陽エネルギーを吸収して成長する植物、その植物から作られる炭や油や蝋、植物性プランクトンを餌として育った魚から採れる油が、燃料エネルギーのすべてでした。基本的に1年間で得られる太陽エネルギーを1年間で消費する社会システムであり、自然再生エネルギーの社会だったといえます。
江戸は15世紀の初めに代官によってつくられましたが、その前から小さな城はあったというのが定説になっています。徳川家康が江戸幕府を開いた時の人口は15万人、家光の時代には40万人、綱吉の時代には90万人、1600年代の後半には100万人都市になっています。その後は安定して100~150万人で推移しました。江戸は、産業革命以前の世界唯一の100万人都市と言われています。
映画やテレビに登場する江戸の裏長屋は、大変不潔に描かれています。しかし、実際は24時間水道が使用できる世界で唯一の町でした。長屋に住む一所帯、一日当たりのゴミの量は、男性の親指の爪の半分だったといいます。イワシの頭から、大根の葉っぱまで消費し、「もったいない」「バチが当たる」などの日本人独特の価値観が生まれた時代です。出来る限りあらゆる物質を反復利用、再活用(リユース)していました。リサイクルシステムが江戸のライフスタイルだったと言えます。
<江戸の風景―物質循環システム->
長屋の大家さんは、オーナーではなく管理人でした。管理人である大家さんは、長屋を借りている店子(たなこ)から家賃を集め、長屋の持ち主であるオーナーから、家賃の歩合をもらっていました。最大の収入源は、長屋に住む人々の糞尿を農家に売ることです。その収入は、オーナーから貰う歩合よりも、はるかに高い金額でした。
農家たちは主に野菜などの物々交換によって、糞尿を手に入れていました。町から出る糞尿は肥料となって、元々痩せた土地であった関東ローム層を豊かな土壌に育て、生産性を向上させました。また、そこで作られた食べ物が運ばれて、江戸は100万人という人口を維持できたのです。
開国時、多くの西洋人が、江戸を「世界一綺麗な都市」と表現しました。それは、都市と周辺の農村を一体としたエコシステム(物やエネルギーの循環系)があったからこその江戸の風景でした。この江戸の社会を地球規模で実践できれば、地球全体が持続可能な社会になるでしょう。それには、人間の価値観とシステムの両方の変化が必要です。どんなに科学が発達しても、環境問題は解決しません。何を価値と思って生きるのかという価値観の変化が、環境問題には必要だということを、この江戸の社会は示していると思います。
<江戸の職業―徹底的な再利用―>
江戸の職業をあげてみると、刃物を研ぐ研師、ノコギリの歯を使い易くする目立て屋、雪駄直し、銅釜を直す鋳掛け屋、煙管の修理と掃除をする羅宇屋、お皿を修理する焼継屋など、修理業が非常に多いことが分かります。幕末の江戸には、古着屋が3987軒、古道具屋が3672軒ありました。蕎麦屋の3763軒と比較しても、その多さが分かります。修繕・リサイクル業が江戸の「基幹産業」だったと言えます。
このような修理業を生業に戻すにはどうしたらいいでしょうか。「修理して形がなくなるまで使っていく」ことに社会が価値を認めなければ、生業として成立しません。逆に、価値を認める人が増えれば生業が復活し、新しい経済が生まれます。経済が先にあって社会ができるのではなく、社会の中の価値観の変化とニーズが経済を作っているのです。ですから、ある一部の地域の中だけであっても、価値観が変化し、ニーズが生じれば、生業が復活することは十分あり得ます。
<江戸の職業―美意識―>
江戸時代は鎖国が続いていて、物が少なく非常に貧しい社会だったと思いがちです。ですが、その中で作られ文化を振り返ってみると、決して暗い時代ではなかったように思います。華族女子教育のお雇いアメリカ人であったアリス・ベーコンは、次のように記しています。
「日本の職人は本能的に美意識を強く持っているので、金銭的に儲かろうが関係なく、彼らの手から作り出されるものはみな美しい。庶民が使う陶器を扱うお店に行くと、色、形、装飾には美の輝きがあり、ここ日本では貧しい人々の食卓でさえも、最高級の優美さと繊細さがある。いまアメリカやイギリスで始められている、大都会に住む貧しい人々の美意識を啓発しようという運動は、この国には全く必要ないことだけは確かである」
日本に来た外国人たちは、美意識は教育によって植えつけるものだとばかり思っていました。ところが日本を訪れてみると、美しいもので溢れていたのです。また、職人たちは、完成されたものでなければ、対価を受け取りません。完成させるために、どれほどの時間がかかっていようとも関係ないのです。製品やサービスが完成されているかどうかは、効率的かつ合理的に経済として成り立っているかどうかではなく、職人が持つ美意識によって判断されていました。産業革命が進み、日給や時給という考え方が当たり前になっていたイギリス人やアメリカ人は、日本の職人の考え方にとても驚きました。
<江戸に暮らした人々―貧困と幸福―>
日米通商条約を結んだタウンゼント・ハリスは、次のように記しています。
「彼らは皆よく肥え、身なりもよく、幸福そうである。一見したところ、富者も貧者もない。これがおそらく人民の本当の幸福の姿というものだろう。私は時として、日本を開国して、外国の影響を受けさせることが、果たして、この人々の普遍的な幸福を増進することになるかどうか、疑わしくなる。私は質素と正直の黄金時代を、いずれの他の国におけるよりも多く日本において見出す。生命と財産の安全、全般の人々の質素と満足とは、現在の日本の顕著な姿であるように思われる」
ハリスについて、私たちが教科書で学んだ限りでは、不平等な日米通商条約を強引に締結した傲慢な男のように思えます。ですが、そのハリスさえも「本当に、この日本を開国させていいのか。」という疑問を持ったほど、江戸時代の日本人は幸福そうに見えていました。
ハリスたちは、日本の労働者が将軍という封建領主に搾取されていて、とても辛い生活を強いられていると考えていました。そこから解放してあげることが、日本に開国を迫った大きな要因でもありました。ところが、実際日本に来てみると様子が違うことに驚きました。
「私はこれまで、容貌に窮乏をあらわしている人間を一人も見ていない。子供たちの顔はみな満月のように丸々と肥えているし、男女ともすこぶる肉付きがよい。彼らが充分に食べていないと想像する事はいささかもできない。下田周辺の住民は、社会階層として富裕な層に属してはおらず、概して貧しい。しかし、この貧民は、貧乏に付き物の悲惨な兆候をいささかも示しておらず、衣食住の点で世界の同階層と比較すれば、最も満足すべき状態にある」(ハリス)
ハリスが見た柿崎の子どもたちの写真を見ると、みんな丸々と肥えて、食べるものには困っていないように窺えます。表情もそれぞれ豊かに写っています。今の都会に住む子どもたちの集合写真と比べると、一体どちらが幸せなのだろうかと考えさせられます。
<江戸に暮らした人々―農村の風景―>
一人で東北、北海道を旅行したイギリスの女性イザベラ・バードは、次のように記しています。
「米沢平野は南に繁栄する米沢の町、北には人で賑わう赤湯温泉をひかえ、まさに『エデンの園』だ。鋤(すき)のかわりに鉛筆でかきならされたような農地。米、綿、トウモロコシ、タバコ、麻、藍、豆類、ナス、クルミ、瓜、キュウリ、柿、柘榴が豊富に栽培されている。繁栄し自信に満ち、田畑の全てがそれを耕作する人々に属する、稔り多き微笑みの地、アジアの『アルカディア』なのだ。人々はつる草やイチジクや柘榴の影で、抑圧を免れて暮らしている。アジア的専制のもとでは注目すべき光景だ」
米沢は、関ヶ原の合戦で負けた上杉潘が、越後の国から移封された場所です。そのとき、上杉潘では「一人の家臣も斬ってはいけない」と家訓で決められていました。膨大な家臣群を連れ、米沢盆地に移った上杉潘士たちは本当に貧しい思いをしたといいます。いよいよ米沢藩が潰れそうになったとき、養子にきた上杉鷹山が再生のきっかけを作りました。鷹山は「武士階級も土地を耕して自分たちで農作物を作れ。垣根には実のなるもの、ご飯の足しになるものを植えろ」と奨励しました。その結果が、イザベラ・バードが『アルカディア』と称した風景でした。
「いたるところに繁栄した美しい村々がある。彫刻のある梁と、どっしりした瓦屋根を備えた大きな家が、柿や柘榴に隠れてそれぞれの敷地に建っており、格子棚に這わせたつる草の下には花園がある。そしてプライバシーは、丈の高い、よく刈り込まれた柘榴やスギの遮蔽物によって保たれている」(イザベラ・バード)
米沢藩が作った食べるため、生きるための風景を、イザベラ・バードは美しいと感じ、本国に帰ってからも多く書物やスケッチなどに残しています。そのスケッチが、今のイングリッシュガーデンの基礎になっています。イザベラ・バードが本国にも残したいと思った米沢の風景が、イングリッシュガーデンとして日本に逆輸入されているのです。
<江戸に暮らした人々―農村の人々―>
初代駐日英国公使のラザフォード・オールコックは、富士登山の折に日本の農村を見て、次のように記しました。
「山岳地帯の只中で、突如として百軒ばかりの閑静な美しい村に出会う。封建領主の圧制的な支配や、全労働者階級が苦しめられている抑圧については、かねてから多くの事を聞いている。だが、これらの良く耕作された谷間を横切って、非常な豊かさの中で所帯を営んでいる幸福で満ち足りた、暮らし向きの良さそうな住民を見ていると、これが圧政に苦しみ、苛酷な税金を取り立てられて困窮している土地だとはとても信じがたい。むしろ、反対に、ヨーロッパの何処にも、こんなに幸福で、暮らし向きの良い農民はいないし、また、これほどまでに温和で贈り物の豊富な風土はどこにもないであろう」
外国人たちは、鉛筆で農作業をやっているのかと思うほど、土地のあらゆる場所に手が入れられ、耕されている風景に感動しました。当時の日本の農村は、自分たちで自分たちのことはやっていくという基本的な自治の考えに基づいて動いていました。その点において、自治が認められないヨーロッパの封建制度とは大きく異なっていたのです。日本の農村は、封建領主に搾取されている労働者階級の集まりではなく、自治力によって美しい風景を作り出していたのです。
<江戸に暮らした人々―子育てと教育―>
先述のオルコックは、日本の子育ての様子を見て、次のように記しました。
「幼い子供の守役は、母親だけとはかぎらない。江戸の街頭や店内で、裸のキューピットが、これまた裸に近い頑丈そうな父親の腕に抱かれているのを見かけるが、これはごくありふれた光景である。父親はこの小さな荷物を抱いて、見るからに慣れた手つきで、やさしく器用にあやしながら、あちこちを歩き回る」(オルコック)
男性が育児に関わる姿は、江戸時代では当たり前の風景でした。それが、西洋文化が入ってきた明治時代の頃から少しずつ変化してきたのです。男は外で働き、女は家を守るという価値観は、この100年程の間に日本人が身につけた割と新しい価値観だと言えます。
長崎海軍伝習所の教官でオランダ人のカッテンディーケは、「しからないで愛情を注ぐ親、自由でのびのびした子供。日本人は、まるでルソー風の自由教育を実現しているようだ」と記しました。ルソーは「子どものための子どもの教育」を1870年代の教育改革で提案しています。子どもが自由に自分の能力を最大限に発揮できるように、能力を引き出してあげることが教育の目的だと主張しました。一方、日本では、まさしく「子どものための子どもの教育」が自然と行われていたことに外国人たちは驚きました。
「日本は、まるで子供崇拝の域に達している。街の道という道は、子供たちに占領されていた。歓声をあげ、走り回る子供。人なつっこく笑顔を振りまく子供……しかも、どんなに貧しい家の子でも必ず『ありがとう』とお礼を言う」(イザベラ・バード)
しかし、これらの風景は、わずか100年の間に、日本の社会から消えようとしています。
<江戸に暮らした人々―庶民のモラル―>
大森貝塚の発見者であり、東京帝国大学教授であったエドワード・モースは、次のように記しています。
「ある秋祭りの夜、女の子二人に10銭ずつ持たせた。どんな風に使うのだろうかと、興味があった。かんざしを売る店に一軒一軒立ち寄って、女の子はあれもこれもと手に取った。飽きずに一品一品、念入りに調べ上げた挙句、たった5厘の品を1、2本買っただけだった。店を出ると、物悲しい三味線を弾く女がいた。路上に座り込んだ乞食であった。二人はその前を通りかかると、それぞれ1銭ずつ取り出して、当たり前のように、女のザルの中に硬貨を落とした」
これは、モース自身が一番驚いたこととして記した出来事です。彼が女の子に渡した10銭は、今の価値で2万円に近い金額です。モースは、使用人の女の子たちが持ったことの無い大金をどのように使うのか、観察したのです。そして、身分相応の5百~千円程のかんざしだけを買い、乞食に千円を渡した女の子たちに驚く結果となりました。モースは、こうした日本人のモラルや価値観の素晴らしさを多く書き残しました。
<まとめ>
当時、世界最大の巨大都市であった江戸は、修繕・リサイクル業が主産業であり、都市と周辺の農村を一体としたエコシステム(物やエネルギーの循環系)がありました。このような社会の「システム」と人々の「節度」の調和から「風土」や「文化」が生まれました。江戸時代に生み出された美術、文学、演劇等の優れた「芸術的な水準」がありました。そして多くの年代の人々は、明るさと好奇心を持ち合わせ、子どもに対する深い愛情がありました。これらの姿は、これからの持続可能な社会のモデルになり得るだろうと考えています。
農山村には、自分たちで自分たちのことをやっていくという意志が、明確にありました。都市の場合は、司法・警察・行政の権限を持った奉行所が各所にありましたが、それを補うように町内単位の自治が確立していました。つまり、住民自らの自治というのは当たり前の社会であったと言えます。そして、様々な職人の様子にもあったように、「生きること」 は「働くこと」と同義の時代でした。この頃、西欧では植民地政策と産業革命が進み、「足りなければ外(植民地)からとってくればいい」「マーケット(植民地)を大きくしてどんどん売っていけばいい」、それが豊かになる根源だと考え始めていました。その延長線上に、私たちの今の暮らしの価値観があります。しかし、鎖国をしていた江戸時代の日本は、有限の世界で自分たちはどう生きるのかを当たり前のこととして考えていました。
現代は、すべてのことをお金に換算して価値を考える世の中になってしまいました。元日産自動車の志賀COO(産業革新機構会長)は次のように話しています。
「リーマン・ショックで、派遣社員の大量の雇い止めをしたのを批判され、経営者は雇用問題に敏感になった。だから社内失業者を抱えた状態だ。円高の中でも雇用維持のために無理して車を作ったから、自動車各社の決算も赤字だった。それも限界点に近づいてきたところに、アベノミクスで円安になり、一息ついているのが今の状態だ。今は、日本にモノ作りを残せるのかどうかの分水嶺だ。今後、労賃は、世界平準化へ向かわざるを得ない。日本の労働者は給与以外の生きがいや幸せを見つけられるだろうか」
労賃が世界平準化されたとき、日本の労働者が給与以外の生きがいや幸せを見つけていなければ、製造業は生き残れません。真庭なりわい塾は、まさにこの生きがいや幸せ、これまでとは違った価値観をつくっていけるかを考えるためにスタートしました。
江戸の社会は、ゼロ・エミッションであり、循環型社会です。そして、自立した大人の社会であり、創造力のある社会です。加えて、好奇心や子どもへの愛情を持った社会でした。これからは環境モデルだけを考えるのではなく、生き方のモデルと新しい価値観を作ることが重要です。そして、新しい価値観によって経済がつくられていくということを、江戸の社会は教えてくれます。
■2年目講座に向けた意見交換
次に、2年目講座に向けた意見交換を行いました。2年目講座では、「木の活用プロジェクト」「里山の恵みプロジェクト」「農と特産品プロジェクト」「地域づくりプロジェクト」の4つのチームで活動することが予定されています。各チームのリーダーは、地域在住の真庭なりわい塾実行委員が務めます。「木の活用プロジェクト」は赤木直人さん(一般社団法人アシタカ)、「里山の恵みプロジェクト」は柴田加奈さん(津黒高原荘いきものふれあいの里)、「農と特産品プロジェクト」は三船進太郎さん(パパラギ農園有限会社)、「地域づくりプロジェクト」は副塾長である大美康雄さん(中和地域づくり委員会)です。塾生たちは希望するグループに分かれ、具体的にどんな活動をしていくか話し合いました。60分間話し合った後、全体で共有し、さらに30分かけてブラッシュアップしていきました。
2年目の各プロジェクトチームの活動成果は、毎年11月3日に開催される中和地区の「紅葉祭」で発表する予定です。
■塾生の感想
<講義「経済と地域~これからの幸福論~」について>
「都市での生活に矛盾や疑問を感じる漠然とした思いが、明確になったような気がします」
「人と人との関係性の中で、幸せを生み出すこと。それに気づくような機会を生み出すことをやっていきたいと思います」
「他の生物は、生きていくために狩りや子育てをしているのに、人間は本来の食や子育てを後回しにして、違うところにすごく労力を使っていると、つくづく感じました」
<ワークショップ「X年後のわたし」について>
「地域や家族との関わり方について、あまり考えていなかったことに気がつきました」
「書き出すことでより具体的にイメージすることができました。今見えている未来を、良い形で実現できるようにしたいです」
「一緒に何かをするのでなくても、同じ感性を持っている仲間がいることは、とても大切だと感じました」
<講義「未来のための江戸の暮らし」について>
「人口が減少していますが、江戸時代のことを思えば、ちょうど良くなってきているのかもしれないと思いました」
「現代のいい部分と、受け継ぐべき過去の知恵を組み合わせていくことが重要だと感じました」
「江戸の質素さに戻ることはできないけど、経済は考え方次第で変えることができることを学びました。今の価値が不変ではないことを痛感しました」
■おわりに
今回も地域のコミュニティハウスに宿泊させていただきました。一の茅集落と荒井集落の皆様、ご協力ありがとうございました。
次回は2月25、26日(土・日)に、塾生による修了レポートの発表と修了式を行います。
=====================================
真庭なりわい塾 第8回講座
「経済と地域~自分でみつける『豊かさ』と『幸せ』の基準~」
開催日:2016年12月10、11日(土・日)
会場:中和保健センター「あじさい」
内容:
(1)講義「経済と地域~これからの幸福論~」
※資料「地域と経済~これからの幸福論~」①.pdf 「地域と経済~これからの幸福論~」②.pdf
(2)ワークショップ「X年後のわたし」
(3)講義「未来のための江戸の暮らし」
※資料「未来のための江戸」①.pdf 「未来のための江戸」②.pdf 「未来のための江戸」③.pdf
(4)「2年目講座に向けた意見交換」
====================================